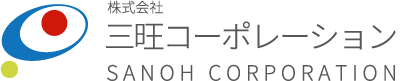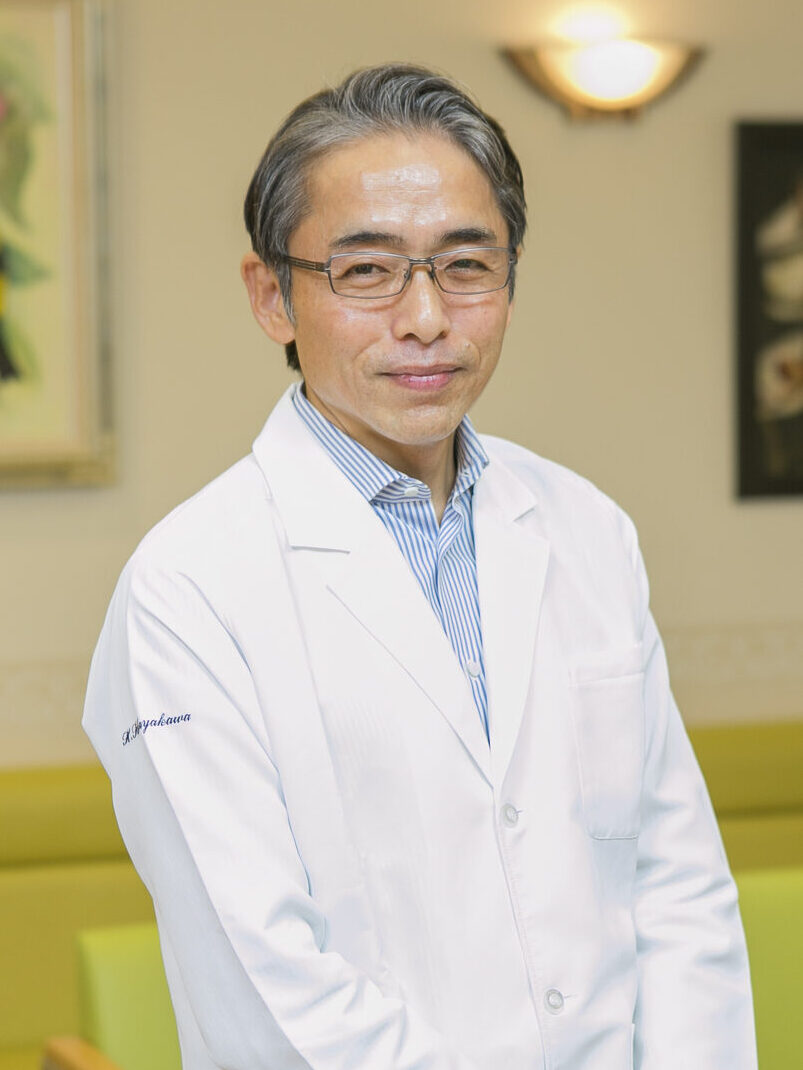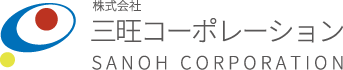Case1
クリニックではどのような診療方針を掲げていますか?
当院は、生活習慣病の患者さんを中心に診療を行うクリニックです。特に糖尿病や高血圧といった生活習慣病の管理に力を入れるとともに、「元気で長生き(アンチエイジング)」をもう一つの重要な柱として掲げています。
生活習慣病は動脈硬化を引き起こし、血管の老化につながります。そのため、糖尿病や高血圧、脂質異常症などの病気を適切に管理することは、アンチエイジングにも直結すると考えています。アンチエイジングは特別な医療ではなく、生活習慣病を地道にコントロールすることが重要です。
生活習慣病は動脈硬化を引き起こし、血管の老化につながります。そのため、糖尿病や高血圧、脂質異常症などの病気を適切に管理することは、アンチエイジングにも直結すると考えています。アンチエイジングは特別な医療ではなく、生活習慣病を地道にコントロールすることが重要です。
「健康寿命」や「未病」へのアプローチについてお聞かせください。
実際に、透析を受けている方や慢性腎臓病(CKD)の患者さんは、血管の劣化が進むことで老化が早まる傾向にあります。そのため、生活習慣病を適切に管理することが、老化を防ぎ健康長寿を目指す第一歩だと考えています。
また、健康診断で生活習慣病の予備軍と指摘され、不安を感じて受診される方も多くいらっしゃいます。そのような方々には、早い段階で生活習慣を見直すことを提案し、未病のうちから健康を維持するためにサプリメントなどを活用した支援を行っています。
また、健康診断で生活習慣病の予備軍と指摘され、不安を感じて受診される方も多くいらっしゃいます。そのような方々には、早い段階で生活習慣を見直すことを提案し、未病のうちから健康を維持するためにサプリメントなどを活用した支援を行っています。
認知症予防にも力を入れておられるそうですね?
はい。認知症は、その人のこれまでの生活習慣や病歴、さらには環境やストレスといった要因が積み重なって現れるものと考えています。例えば、糖尿病の方は認知症のリスクが高く、また喫煙・飲酒・甘いものの過剰摂取なども脳の萎縮を引き起こす要因になります。そこで、当院では認知症になりにくい生活習慣の提案や、予防のためのサプリメント・点滴療法なども提供し、総合的な健康管理をサポートしています。
サプリメントを取り入れるようになった経緯を教えてください。
従来の医薬品による治療に限界を感じていました。かといって、自然療法だけで全てを解決できるとも思っていませんでしたが、西洋医学だけでは現代の患者さんのニーズに対応しきれないと痛感するようになりました。そんな折、栄養療法の勉強会に参加したことがきっかけで、サプリメントを診療に取り入れるようになりました。
当時、名古屋では「サプリメント」という言葉自体が一般的ではなく、疑わしいものとして認識されていました。しかし、教科書通りの医療だけでは患者さんの多様なニーズに応えられない、医療の幅を広げたいという思いが強く、サプリメントの導入に踏み切りました。
当時、名古屋では「サプリメント」という言葉自体が一般的ではなく、疑わしいものとして認識されていました。しかし、教科書通りの医療だけでは患者さんの多様なニーズに応えられない、医療の幅を広げたいという思いが強く、サプリメントの導入に踏み切りました。
サプリメント導入にあたって、どのような思いがありましたか?
内科外来には、なんとなく調子が悪いという方が多く来院されます。しかし、開業医の立場では、検査結果が基準値内であれば「異常なし」としか言いようがありません。保険診療だけを考えれば、その方が経営的には安定するのかもしれません。しかし、それでは患者さんに寄り添う医療とは言えません。
来院された患者さんには、少しでも「何かを持ち帰ってほしい」という思いから、言葉だけでも丁寧に寄り添うようにしていました。そこにサプリメントという選択肢を加えることで、より幅広い診療を提供できるようになりました。
当時、サプリメントを求める患者さんはほとんどいませんでしたが、まさか今のようにサプリメントが一般的に扱われるようになるとは想像もしていませんでした。今後は、サプリメントを導入する医療機関が増えていくと思います。
来院された患者さんには、少しでも「何かを持ち帰ってほしい」という思いから、言葉だけでも丁寧に寄り添うようにしていました。そこにサプリメントという選択肢を加えることで、より幅広い診療を提供できるようになりました。
当時、サプリメントを求める患者さんはほとんどいませんでしたが、まさか今のようにサプリメントが一般的に扱われるようになるとは想像もしていませんでした。今後は、サプリメントを導入する医療機関が増えていくと思います。
サプリメント選びの際、どんな点を重視されていますか?
まず、製造業者がきちんとしていること、できるだけ科学的な裏付けがある(エビデンス)製品であることです。タキシフォリンを気に入っているのは、生産国のロシアでエビデンスがあることや、国立循環器病研究センターで臨床研究が行われている点です。
当院ではタキシフォリンを認知機能の改善の目的で使用することが多いですが、実際には劇的に良くなる人はいますが、そうでない人もいます。しかし、認知機能が改善していなくても、患者様が「元気になった」と感じることがよくあります。これはご家族にとって非常に喜ばしいことです。
逆に認知機能検査(HDS-Rなど)の点数が(例えば15点から20点に)改善しても、日常生活に大きな変化が見られない場合もあります。認知症の治療において、ご本人やご家族にとって重要なのは、QOL(生活の質)やウェルビーイング(心身ともに満たされた状態)であると言えます。
当院ではタキシフォリンを認知機能の改善の目的で使用することが多いですが、実際には劇的に良くなる人はいますが、そうでない人もいます。しかし、認知機能が改善していなくても、患者様が「元気になった」と感じることがよくあります。これはご家族にとって非常に喜ばしいことです。
逆に認知機能検査(HDS-Rなど)の点数が(例えば15点から20点に)改善しても、日常生活に大きな変化が見られない場合もあります。認知症の治療において、ご本人やご家族にとって重要なのは、QOL(生活の質)やウェルビーイング(心身ともに満たされた状態)であると言えます。
実際の診療でタキシフォリンはどのように活用されていますか?
タキシフォリンは、最初は認知症サプリとして採用しましたが、今は広く応用できるようになりました。糖尿病で認知症の予兆があったら100%使っており、8割はタキシフォリンを使っています。認知症の陰性症状と陽性症状を調整してくれるなど、良い効果が見られるので使いやすいと感じています。
また、血管保護作用やアミラーゼ、αグルコシダーゼ、リパーゼの抑制作用があることで、糖尿病対策にも使えるのも良いと思います。
また、血管保護作用やアミラーゼ、αグルコシダーゼ、リパーゼの抑制作用があることで、糖尿病対策にも使えるのも良いと思います。
患者様にはどのようにサプリメントを提案されていますか?
医者が薦めるには科学的根拠に基づいて、例えば血液診断の結果など合理的な説明が必要です。ただ、時間がないのでゆっくり説明はできていないのですが、限られた診療の中でパンフレット等をつかってわかりやすく説明しています。本当は栄養士とかスタッフがするのが理想ですが、その点は今後の課題と考えています。
今後、サプリメントにどのような医療的価値を期待していますか?
当院では、医薬品による治療はもちろん行っていますが、健康維持の基本は、バランスの取れた栄養摂取と病気の予防であると考えています。そのため、患者様にはマルチビタミンやミネラルなどのサプリメントを積極的にご提案することがあります。
栄養問題は高齢者特有のものと思われがちですが、若い世代にも栄養障害が多く見られます。実際の診察でも、体調不良の原因が栄養障害であるケースが目立ちます。それぞれの病状に合わせて、必要な栄養素を効率的に摂取するためのサプリメントも、必要に応じてご提案しています。
当院が目指すのは、「できるだけ病気になりにくい体作り」、つまり予防医療です。そのため、安易な薬物療法に頼るのではなく、薬の使用を最小限に抑えることを心がけています。
例えば、火事に例えると、まだ火が燃え上がっていない状態、つまり症状が現れる前の段階では、むやみに薬を使うべきではないと考えています。
そして、薬を減らすことが患者様にとってどれほど有益かを、丁寧に説明するように心がけています。
栄養問題は高齢者特有のものと思われがちですが、若い世代にも栄養障害が多く見られます。実際の診察でも、体調不良の原因が栄養障害であるケースが目立ちます。それぞれの病状に合わせて、必要な栄養素を効率的に摂取するためのサプリメントも、必要に応じてご提案しています。
当院が目指すのは、「できるだけ病気になりにくい体作り」、つまり予防医療です。そのため、安易な薬物療法に頼るのではなく、薬の使用を最小限に抑えることを心がけています。
例えば、火事に例えると、まだ火が燃え上がっていない状態、つまり症状が現れる前の段階では、むやみに薬を使うべきではないと考えています。
そして、薬を減らすことが患者様にとってどれほど有益かを、丁寧に説明するように心がけています。