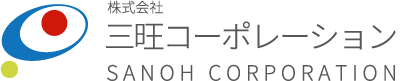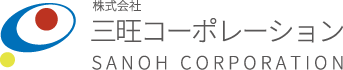Case2
これまでのご経歴と診療への想いについて教えていただけますか?
私は医学部卒業後、2年間の研修を経て循環器内科医として、救急医療の最前線で心筋梗塞や心不全の患者さんと向き合ってきました。2005年からは千葉県国保匝瑳市民病院で内科外来も担当するようになり、高齢化の進行とともに認知症の患者さんと接する機会が増えていきました。
そのような中、認知症になった80代の高血圧症患者さんの娘さん(匝瑳市民病院の看護師)から、認知症の診察を頼まれました。専門外ながらも、できる範囲で対応しようと模索する中でコウノメソッド*に出会い、愛知県共和病院のホームページに掲載されていた河野和彦先生のレビー小体型認知症の講義に感銘を受けました。
そこでは、認知症治療において薬物療法の難しさを知ることとなり、この出会いが大きなターニングポイントとなりました。当初は認知症診療に抵抗がありましたが、訪問診療クリニックの院長就任を機に本格的にコウノメソッドを学ぶようになりました。
*コウノメソッドとは:河野和彦医師によって提唱された陽性症状の強い認知症でも家庭介護が続けられるように処方することを 主眼として一般公開される薬物療法マニュアル
そのような中、認知症になった80代の高血圧症患者さんの娘さん(匝瑳市民病院の看護師)から、認知症の診察を頼まれました。専門外ながらも、できる範囲で対応しようと模索する中でコウノメソッド*に出会い、愛知県共和病院のホームページに掲載されていた河野和彦先生のレビー小体型認知症の講義に感銘を受けました。
そこでは、認知症治療において薬物療法の難しさを知ることとなり、この出会いが大きなターニングポイントとなりました。当初は認知症診療に抵抗がありましたが、訪問診療クリニックの院長就任を機に本格的にコウノメソッドを学ぶようになりました。
*コウノメソッドとは:河野和彦医師によって提唱された陽性症状の強い認知症でも家庭介護が続けられるように処方することを 主眼として一般公開される薬物療法マニュアル
クリニックの診療方針や特色について教えていただけますか?
現在は認知症診療を専門に、千葉県市川市にて「来院されたすべての方を治したい」という信念のもと、日々診療に取り組んでいます。2015年の開業にあたっては、河野先生の外来を見学させていただき、千葉県でも改善率の高い認知症治療を提供できるようにしたいと考えました。
「認知症は治らない」という定説に疑問を持ち、コウノメソッドをさらに深く学びました。この方法は、東洋医学的な調和を重視し、薬だけでなくサプリメントや漢方も活用する治療法です。臨床を重ねるなかで、実際に約8割の方の認知症症状に改善が見られ、確かな手応えを得ています。
また、より多くの在宅診療医が認知症診療に取り組めるよう、自身の経験を共有する場として「ドクターマツノ認知症ゼミ」や各種セミナーを開催しています。
「認知症は治らない」という定説に疑問を持ち、コウノメソッドをさらに深く学びました。この方法は、東洋医学的な調和を重視し、薬だけでなくサプリメントや漢方も活用する治療法です。臨床を重ねるなかで、実際に約8割の方の認知症症状に改善が見られ、確かな手応えを得ています。
また、より多くの在宅診療医が認知症診療に取り組めるよう、自身の経験を共有する場として「ドクターマツノ認知症ゼミ」や各種セミナーを開催しています。
タキシフォリンを取り入れた経験について教えていただけますか?
タキシフォリンは、コウノメソッド実践医の中から進行性核上性麻痺(PSP)*の歩行動作に対する有用性が報告されたことがきっかけで知りました。その後いろんな情報を提供してもらう中で糖尿病や動脈硬化をはじめ血管に関する疾病にも有効であると思うようになりました。
*進行性核上性麻痺(PSP)
脳の中で特に大脳基底核、脳幹、小脳といった部位の神経細胞が減少することで起こる、進行性の神経変性疾患
*進行性核上性麻痺(PSP)
脳の中で特に大脳基底核、脳幹、小脳といった部位の神経細胞が減少することで起こる、進行性の神経変性疾患
サプリメントを導入する際の基準はありますか?
まず「誰が作っているか」を重視しています。研究会などで面識のあるメーカーであれば、製品の背景や開発者の想いが理解でき、信頼できます。
同じ成分であっても、製法の違いによって品質は大きく異なりますので、誠実に研究を重ねている企業であるかが重要です。
同じ成分であっても、製法の違いによって品質は大きく異なりますので、誠実に研究を重ねている企業であるかが重要です。
実際にタキシフォリンを使ってみて、患者さんの反応はいかがでしょうか?
認知症治療においてはファーストチョイスというわけではありませんが、病型や症状に応じて選択肢のひとつとして使用頻度は増えてきました。劇的に改善する症例は経験していませんが、意欲が出たり表情が明るくなるという印象を持っています。その他には、糖尿病の合併症の予防や、血管を若々しく保ちたいと希望する患者さんにも勧めています。
医療現場におけるサプリメントの役割をどのように考えていますか?
私はサプリメントを「治療の土台」と捉えています。肌に例えるなら、化粧の前に地肌を整えるようなもので、体の土台がしっかり整っていれば薬や漢方が適切に作用します。逆に、土台が悪いと薬も効きにくいし、副作用ばかり出てしまう。サプリメントを使うことで薬の量を最小限にすることができます。特に認知症のような長期戦の疾患においては、抗酸化作用を有するサプリメントは非常に重要な役割を果たします。
患者さんへのサプリメント提案について、どのようにお伝えされていますか?
経済的な負担が問題ない場合は、積極的に提案しています。サプリメントを活用することでより良い結果が期待できるからです。医薬品に比べ副作用の心配が圧倒的に少なく、アンチエイジング効果も期待できることからメリットが高いと考えています。体が本来持っている自然治癒力を高めるためにも有効だと説明しています。一方でサプリメントの効果に懐疑的な方や、西洋薬や漢方薬を避けたいと考える方もいます。こうした多様な考え方を尊重し、患者さんの希望や状態に応じて、個別化医療を提案しています。
今後の診療やサプリメント活用への展望について教えていただけますか?
今後の医療において、サプリメントはますます重要な役割を担うと考えています。開業当初は「認知症に良いのではないか」と漠然と捉えていたサプリメントですが、現在は認知症を“栄養不足の状態”と位置づけ、栄養補給の大切さを実感しています。加齢とともに減少し、薬や漢方では補えない成分を補ううえで、特に血管の栄養となるタキシフォリンのようなサプリメントは不可欠な存在です。
私は、全身の毛細血管まで血流を改善することが健康寿命の延伸に繋がると考え、血管をしなやかにすることを重視しています。高齢者では血圧を下げすぎることで、脳血流が低下し、かえって悪影響を及ぼすことがあるため、安易な降圧は避けるべきです。過量の降圧剤は認知症のリスクを高める可能性があることから、タキシフォリンのような血流改善サプリメントで状態が安定すれば、降圧剤を減らしていき、最終的にはゼロにすることを目指しています。
私は「エビデンスが全てではない」と考えており、臨床現場での直感や経験則を大切にしています。ガイドラインやエビデンスに基づく標準治療で改善しない患者さんには、最適な個別化医療を組み立てていきます。
私の治療方針は、時に異端と見られることもあるかもしれません。しかし、標準治療で改善しない患者さんのためにこそ、新たな選択肢が必要です。そのなかでサプリメントは欠かせないと考えています。現在は、講演活動などを通して、その重要性を多くの医師や関係者に伝える取り組みも行なっています。
サプリメントへの関心が高まることで、世の中の目も「安価なもの」ではなく「品質や有効性」に向くようになっていくことが予想されます。そうなれば、貴社のように真摯に取り組む企業が自然と選ばれるはずです。タキシフォリンは今後ブレイクすると信じており、その有効性は間違いないと感じています。
私は、全身の毛細血管まで血流を改善することが健康寿命の延伸に繋がると考え、血管をしなやかにすることを重視しています。高齢者では血圧を下げすぎることで、脳血流が低下し、かえって悪影響を及ぼすことがあるため、安易な降圧は避けるべきです。過量の降圧剤は認知症のリスクを高める可能性があることから、タキシフォリンのような血流改善サプリメントで状態が安定すれば、降圧剤を減らしていき、最終的にはゼロにすることを目指しています。
私は「エビデンスが全てではない」と考えており、臨床現場での直感や経験則を大切にしています。ガイドラインやエビデンスに基づく標準治療で改善しない患者さんには、最適な個別化医療を組み立てていきます。
私の治療方針は、時に異端と見られることもあるかもしれません。しかし、標準治療で改善しない患者さんのためにこそ、新たな選択肢が必要です。そのなかでサプリメントは欠かせないと考えています。現在は、講演活動などを通して、その重要性を多くの医師や関係者に伝える取り組みも行なっています。
サプリメントへの関心が高まることで、世の中の目も「安価なもの」ではなく「品質や有効性」に向くようになっていくことが予想されます。そうなれば、貴社のように真摯に取り組む企業が自然と選ばれるはずです。タキシフォリンは今後ブレイクすると信じており、その有効性は間違いないと感じています。