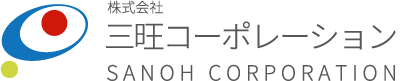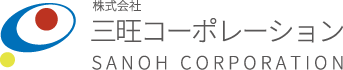歯周病は万病のもと。近年の研究で、歯周病が全身の健康に影響を及ぼすことが明らかになっており、「予防歯科」の重要性がますます高まっています。
プロによるケアは3カ月から半年に1回程度が推奨されており、定期的に受けることで、虫歯や歯周病の早期発見・治療が可能になります。しかし、その間はセルフメンテナンスが重要です。プロによるケアの間隔が空くため、自分でしっかりと維持することが求められます。
そもそも歯周病とは?
歯周病とは、歯周ポケットから細菌が侵入し周辺組織が炎症を起こす疾患です。歯周病の原因は歯垢(プラーク)と呼ばれる細菌の塊と言われています。
プラークとは、口の中の常在菌とその産生物からなる、歯の表面に付着した白く柔らかな沈着物のことを指します。よく「食べカス」と同じだと勘違いされがちですが、全くの別物です。
歯垢は多くの場合、唾液で洗い流されますが、沈着した場所によっては増殖し、炎症の原因になってしまいます。また、歯周病が進行すると、歯の周辺だけでなく血液によって細菌が運ばれ、全身に影響を与えることも分かっています。
歯周病の特徴

歯周病は、初期の段階では自覚症状が少ないため、気づかないうちに進行してしまうこともあります。次の項目のうち、一つでも当てはまると歯周病の可能性がありますので、毎日の歯みがき時にチェックしてみましょう。
1.歯茎の腫れと出血
・歯周病により歯ぐきが炎症を起こすと、歯磨きやフロスを使ったときに出血しやすくなります。
・炎症が進行すると歯ぐきが赤く腫れてしまいます。健康な歯ぐきはピンク色をしており、引き締まっておりますが、腫れた歯ぐきはブヨブヨした状態になります。
2.口が臭くなる
・歯周病が進行すると、原因となる最近が増殖し、口臭のもととなります。
3.歯がぐらつく、歯ぐきが下がる
・歯周病により歯の組織が壊され、歯ぐきがぐらついたり、歯ぐきが下がってしまいます。
4.膿が出る
・炎症が進行すると、細菌が増殖し歯ぐきから膿が出ることがあります。
5.歯の痛み
・歯周病が進行すると、周辺組織がダメージを受け、エナメル質が少なくなることで、痛みを感じやすくなります。
歯周病を予防する方法は?

歯周病は日々のセルフケアと定期的な歯科検診を組み合わせることで予防可能です。以下の方法を実践し、健康な歯と歯茎を維持しましょう。
1.歯みがきをする
歯周病予防のためには、1日2回以上の歯みがきが推奨されています。特に夜は唾液の分泌が減り、歯周病菌が繁殖しやすくなるため、より丁寧に行うことが大切です。
歯ブラシは、歯周ポケットも清潔に保てるように、毛先が細いタイプが良いでしょう。硬さは、硬すぎないものを選び、歯ぐきを傷つけないように磨くことが大切です。
歯医者さんに行くと歯みがき指導で正しい歯磨きの方法を教えてくれます。
歯みがきの方法その1.バス法
・歯ブラシを歯と歯茎の境目(歯周ポケット)に45度の角度で当てる
・小刻みに優しく磨く
歯周ポケットまでしっかり磨けるので、歯周病ケアに向いている方法です。
歯みがきの方法その2.スクラビング法
・歯に対して垂直にブラシを当てる
・小刻みに横に動かしながら磨く
基本的な歯みがき法であり、バス法と合わせて行いましょう。
ゴシゴシしたり、力強く磨くと歯ぐきが傷つき細菌繁殖の原因になります。自分が思うよりも優しく、歯を1本1本丁寧に磨く気持ちで行うようにしましょう。デンタルフロスや歯間ブラシも合わせて行うと歯ブラシだけでは取れない細かい隙間を清潔に保つことが出来ます。
2.生活習慣を見直す
歯周病を悪化させる原因の一つが「食事」です。以下のポイントを意識して食生活を改善しましょう。
・糖分を控え、適度に咀嚼回数が多い食べ物を
糖分の多い食品は、細菌のエサとなるため細菌が増殖しやすくなります。また、咀嚼回数が少なく済む柔らかい食べ物は唾液の分泌が減り、細菌が口腔内に残りやすくなってしまいます。よく噛む食品を定期的に摂ることで、唾液の分泌を促進し、口の中を清潔に保つことが出来ます。
・禁煙する
日本臨床歯周病学会によると、歯周病にかかる危険は1日10本以上喫煙すると5.4倍に、10年以上吸っていると4.3倍に上昇し、また重症化しやすくなると言われています。タバコの煙に含まれるニコチンには、血管収縮作用があるため、喫煙すると血流が悪くなります。すると、栄養素が歯ぐきに届きずらくなり、周辺組織にダメージが起こります。
せっかく歯周病ケアを丁寧に行っていても、喫煙することで細胞の修復力が阻害されてしまっては本末転倒です。
3.定期的な歯科検診

歯科検診は、3カ月~半年に1回が理想的だとされています。歯科検診に行くと、歯周ポケットの深さを検査してくれますが、健康的な歯ぐきの場合、深さは1mm~2mmと言われています。深さ3mmを超えると要注意、4mmを超えると歯周病と診断されます。3mmであれば、セルフケアでも改善できることも多いですが、4mm以上になると、医療介入が必要となる場合もあります。痛みがないと行かない人も多いですが、痛みが出る前に行くことが大切。歯周病は初期症状がなく、自覚症状がでないまま進行していることも多いため、早めのチェックが大切です。
水素で歯周病予防に?
最近ではさまざまなデンタルケアグッズがありますが、水素アイテムも歯周病予防に効果があると注目を集めています。2012年、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学分野の森田学教授らの研究により、水素水の摂取が歯周病予防につながることが示唆されました。
水素水を与えたラットの血中の活性酸素が抑制され、さらに歯茎の歯周病の進行も抑制されたというのです。「水素水で口をゆすぐことで、歯茎にもよい影響があるのでは?」と考え、水素関連のデンタルケアアイテムを調べてみると、「水素×口腔ケア」アイテムが販売されています。見えない部分や歯ブラシが届かない箇所のケアはとても難しく、実は歯科医師でも自身の歯を完璧に磨くのは難しいと言われています。だからこそ、日々の歯磨きにプラスして「水素アイテム」を取り入れることで、より効果的に歯周病を予防できるかもしれません。
まとめ
・ 歯周病は、歯周ポケットに細菌が侵入し炎症を起こす病気。進行すると全身に悪影響を及ぼす
・定期的な歯科検診(3カ月~半年に1回)でプロのケアを受けるのが理想
・セルフケアが重要! 正しい歯磨き習慣を身につけることが必須
・水素アイテムが歯周病予防に役立つ可能性がある
・歯周病は早期予防と治療がカギ
毎日のセルフケアをしっかり行い、定期的に歯科検診を受けることで、健康な歯と歯茎を維持しましょう。
【参考】
・からだケアナビ「ポリフェノールの効果と摂り方」https://x.gd/omp2K
・花王「ポリフェノールの健康価値」https://x.gd/yFooQ
・健康長寿ネット「ポリフェノールの種類と効果と摂取方法」https://x.gd/Adnta